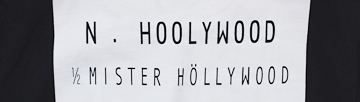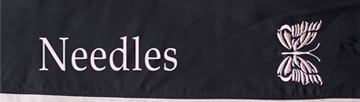No.09 1985年の音楽シーン Part 2 国内篇 by 青野賢一
BACK TO 1985|
イマに続く1985年の40のコト。
ファッションは常に時代のカルチャーとも密接。RAGTAGが誕生した1985年の音楽事情について、ファッションにも精通した文筆家で、DJとしても活動する青野賢一さんの目線で、8枚の必聴アルバムとともにお届けします。今回は国内音楽篇。

Profile
青野賢一
1968年東京生まれ。株式会社ビームスに長年勤務し、PR、クリエイティブ・ディレクターを歴任、BEAMS RECORDSの立ち上げからディレクターも務める。2021年10月に退社、独立し、現在はフリーランスとして、音楽、ファッション、映画、文学、美術といった文化芸術全般をフィールドにした文筆家、DJ、選曲家として活躍している。
- https://www.instagram.com/kenichi_aono/
index
渾然一体が生んだ化学反応
マスとカルト、職業作家とアーティスト、プロと素人、表舞台に立つ人とそれまで本人が出てくることのなかった文化人や裏方的な人––––そんな人たちがひとところに共存し、混ざりあうことで化学反応を生んでいたのが1985年だったように思う。その状況を可能にしていたのが雑誌文化の発展とテレビの存在で、そうしたなかで人はメジャーな情報を取り入れつつも、自分だけのカルトな「好き」を追い求めることができた。インターネット普及以前の、ある意味幸福な時間が1985年といえるかもしれない。
テレビの圧倒的な影響力
ご存じのように当時はテレビが巨大な影響力を誇っており、音楽もテレビと密接な関係を築いていた。その好例がテレビ番組『夕やけニャンニャン』が生んだアイドル・グループ「おニャン子クラブ」。高校生世代を中心とした素人的なメンバーで構成される大所帯のこのグループは、それ以前のアイドルとはずいぶんとかけ離れており、斬新だった。1983年に「ギザギザハートの子守唄」でデビューし、1985年にはすでに人気絶頂だったチェッカーズの「あの娘とスキャンダル」が同番組のオープニング・テーマに採用されたことも話題となった。リズム&ブルースやロックンロールを下敷きにしたチェッカーズの音楽はとりたてて目新しいものではなかったが、それをアシンメトリーなヘアスタイルやデコラティヴなファッションといったその時代のムードでもって表現したのが実に秀逸だった。チェッカーズの仕掛け人はプロデューサー、編集者の秋山道男。雑誌『活人』の表紙で小泉今日子を全身黒塗りにしたのもこの人の仕事である。また、TBSドラマ『毎度おさわがせします』の主題歌「Romanticが止まらない」がヒットしたC-C-B、お茶の間にエレクトロ・ビートとブレイクダンスを届けた風見慎吾「涙のtake a chance」(1984年12月リリース)などはまさにこの時代のテレビの産物といえるだろう。
『KICK OFF』 おニャン子クラブ
大所帯アイドル・グループのはしり、おニャン子クラブ。こちらは『夕やけニャンニャン』からヒットした「セーラー服を脱がさないで」を含むファースト・アルバムだ。作詞は秋元康、作曲家陣は松尾清憲、後藤次利、山川恵津子といった凄腕ポップス職人が名を連ね、少しノスタルジックなポップスを展開している。参加ミュージシャンも山木秀夫、青山純、鳥山雄司、松原正樹ら名うてのセッション・ミュージシャンばかりという豪華さ。
『毎日‼︎チェッカーズ』 チェッカーズ
飛ぶ鳥を落とす勢いだったチェッカーズの3枚目のスタジオ・アルバム。チェッカーズはもともとドゥーワップやリズム&ブルース、ロックンロールを軸にしたバンドで、そこにあのインパクトのあるファッションやヘアスタイル、そしてメンバーのキャラクターが加わって大きな人気を博した。本作は音楽的には先に記した路線を踏襲しながら、親しみやすいポップスとしてうまくまとめたもの。シングル・ヒットした「ジュリアに傷心」を収録。
『シングルコレクション』 C-C-B
木村一八と中山美穂を主役に据えたテレビドラマ『毎度おさわがせします』のテーマ・ソングに「Romanticが止まらない」が採用されたことで一躍人気グループとなったC-C-B。カラフルなファッションとヘアスタイルで、テレビの歌番組に出演しても目を惹く存在感がありアイドル的な人気を得たが、実はこのバンドは演奏力が大変高いのがポイント。その意味ではイギリスのシンセポップ・バンド、デュラン・デュランを思い起こさせる。
『成増 とんねるず1番』 とんねるず
1982年、『お笑いスター誕生‼︎』でグランプリに輝き、1983年からは『オールナイトフジ』、続いて『夕やけニャンニャン』のレギュラーを務め、無軌道なパフォーマンスと内輪ネタで視聴者を笑わせる力技で若者から高い支持を得ていたとんねるず。その彼らが歌の世界に本格進出したアルバムがこちら。サウンド・プロダクションを一風堂のキーボーディスト、見岳彰が担当し、当時の英国産シンセポップを参照した先端の音を展開している。
次のステップを模索するアイドルたち
先ほど小泉今日子の名を出したが、彼女や中森明菜、松本伊代(デビューは1981年秋)、早見優、石川秀美、堀ちえみなど1982年デビューの女性アイドルたちは「花の82年組」と称され、人気を博していた。そんな82年組がキャリアを重ねるなかで次のステップを模索していたのが1985年だった。
1983年にショートカットにするなど、ほかの同期に先んじてイメージチェンジを図ったのは小泉今日子。中森明菜は、日本のラテンジャズ・ピアノの第一人者でのちに人気アニメーション作品『ハートカクテル』の音楽を手がけることとなる松岡直也作編曲の「ミ・アモーレ」で同年の日本レコード大賞を受賞した。当時のアイドルの楽曲を取り巻く環境としては、旧来の歌謡曲的な作家陣による作詞作曲編曲だけでなく、この「ミ・アモーレ」のようにアーティストやグループの一員としてすでに名の知られた存在であった人物の参入が当たり前になりつつあった。
また、1983年に「散開」したイエロー・マジック・オーケストラ(YMO)が確立した、シンセサイザーやコンピューターをポピュラー・ミュージックに導入するというアプローチが普及していたことも特筆すべきところではないだろうか。
『D404ME』 中森明菜
名曲「ミ・アモーレ」を収録した中森明菜の8作目のスタジオ・アルバム。大貫妙子、後藤次利、清水信之、EPO、忌野清志郎、松岡直也、そして久石譲といった錚々たる作家陣を迎えた本作は、参加ミュージシャンも実に豪華(「BLUE OCEAN」では久石譲がキーボードを弾いている)。こうした高いクオリティに一歩も引けをとらない中森明菜の表現力には驚かざるをえない。アイドルの先には優れたポピュラー・ミュージックがあった。
テレビがカルトをマスに引き上げた
先に述べたように、この時代はテレビの影響力が大きかったのだが、実は、マス向けのキャッチーでわかりやすいものだけでなく先鋭的なカルチャーを大衆に広く知らしめる役割も担っていた。1985年10月にスタートしたフジテレビ系深夜の『冗談画報』には米米CLUB、WAHAHA本舗、坂田明、聖飢魔Ⅱ、ラジカル・ガジベリビンバ・システム、有頂天などが出演しパフォーマンスを披露。テレビ朝日系の月曜から金曜の深夜帯では曜日ごとに不思議なおかしみのあるバラエティ(月、水)、ドラマ(火)、若い女性向けの情報番組(木)、そして金曜日は『タモリ倶楽部』を展開しており、一部の好事家のあいだで人気を博した。このようにテレビがマスとカルトのハブとして機能していたのである。
『シャリ・シャリズム』 米米CLUB
1982年に結成、1985年リリースの本作でメジャーでのアルバム・デビューを果たした米米CLUB。カールスモーキー石井とジェームス小野田をフロントマンに、ホーンやダンス・クルーを取り入れたステージ・パフォーマンスと、タイトかつファンキーな演奏で熱狂的なファンを生んだ。コスチュームやメイクなどビジュアル面を徹底的に追求したエンタテインメント性のあるステージはキッド・クレオール&ザ・ココナッツを彷彿とさせる。
多様な面白さと洋楽からの影響
ポピュラー・ミュージックに関していえば、先に記したアイドルたち、それから松任谷由実や山下達郎といったかねてより活躍していた優れたシンガー・ソングライターに加えて、佐野元春、尾崎豊、大沢誉志幸、吉川晃司など気鋭のアーティスト、のちのバンド・ブームを予感させるレベッカ、ラフィン・ノーズ、米米クラブや聖飢魔Ⅱなどの活躍が目立ってきたのが印象的だった。こうして挙げてみると実に多様で面白い年である。また、シンガー・ソングライターであれバンドであれ、あるいはアイドルであれ、その楽曲からは洋楽の影響が大いに感じられた。つまり音楽の作り手がよいリスナーだった時代でもあったのだ。
『Cafe Bohemia』 佐野元春
今年でデビュー45周年となる佐野元春は文学性の高い歌詞と柔軟に時代を取り入れたサウンドで高い評価を得ているシンガー・ソングライター。1985年の「国際青年年」のテーマ曲となった「Young Bloods」を含む本作は、アルバム・タイトルやジャケットのムードからもわかるように、スタイル・カウンシルをはじめとするイギリスのバンドやアーティストに影響を受けた内容。ジャズやレゲエのエッセンスをうまく取り入れた意欲作だ。
『回帰線』 尾崎豊
高校在学中にデビューし、そのメッセージ性の強い歌詞から同世代を中心にカリスマ的な存在として崇められたシンガー・ソングライター、尾崎豊。こちらは1985年発表のセカンド・アルバムだ。本作の代表曲であり自身初のランク・イン曲となったシングル「卒業」は、当時の学校を取り巻く雰囲気とそこでの当事者たちの思いやこれから先の人生への問いかけをまっすぐに綴った歌詞で、「10代の教祖」と呼ばれるほどの影響力を誇った。
『REBECCA Ⅳ ~Maybe Tomorrow~』 Rebecca
日本テレビ系ドラマ『ハーフポテトな俺たち』のエンディング・テーマから火がついた「フレンズ」の大ヒットで知られるREBECCA。本作は同曲を収録した4作目のアルバムでミリオンセラーとなった。NOKKOの存在感のあるボーカルを生かした、マドンナやシンディ・ローパーを思わせるシンセポップが多い印象だが、同時にボトムヘビーなバンド・サウンドでもある。NOKKOのファッションやヘアスタイルもフォロワーが多かった。
『Laughin’ Nose』 Laughin’ Nose
有頂天、The Willardと並んで「インディーズ御三家」と呼ばれ、熱狂的な支持者を集めたパンク・バンド、Laughin’ Nose。パンク、インディーズを日本に根付かせたこのバンドのメジャー・デビュー作がこちら。インディーズ時代からの人気曲「Get The Glory」を含む本作はシンプルで威勢のいい内容だが、イギリス、ニューヨークで1970年代に興ったパンク・ムーブメントの音とは質感が異なり、しっかりこの時代の音なのが興味深い。
青野賢一さんによる「1985年の音楽シーン Part 1 洋楽篇」はこちら。




![No.15 [DAIRIKU]デザイナー 岡本大陸 さんが語る1985年周辺映画](/wp-content/uploads/2025/09/no15.jpg)