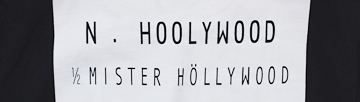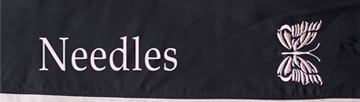No.20 「1985年生まれの名品たち。」New Balance M1300
BACK TO 1985|
イマに続く1985年の40のコト。
1985年に生まれて、現在もその輝きの失せない名品を、RAGTAGのスタッフがご紹介。
今回はNew Balance M1300について。
text : サイト運営チーム マネージャー SAMPEI
photo : TAWARA(magNese) / edit : Yukihisa Takei(HIGHVISION)

Profile
SAMPEI
サイト運営チーム / マネージャー
ファッションも食べることも大好きで、Google Mapの「行ってみたい」リストには1,000件を超えるお店のピンが立っている。 ファッションに関しては収集癖があり、New Balanceやpatagoniaのバギーズショーツなどを集めている。 シンプルながらも一癖あるアイテムを着用しがちで、気になったものはまず試してみるタイプ。
index
New Balanceの名品 “M1300” とは?

1985年に登場した “M1300” は、[ニューバランス]の歴史を語るうえで欠かせない一足です。発売当時の価格は130ドル。その時代のスニーカーとしてはかなり高額だったのですが、履いた瞬間に「これは違う」と感じた人が多かったそうです。
代表的なものとしては、あのラルフ・ローレンが「雲の上を歩いているようだ」と評した逸話が残っているほど。スニーカーを“クラフト”として語るきっかけになったモデルとも言われています。
さらに、当時の広告もかなりインパクトがありました。
“Mortgage the House.(家を担保にしてでも買う価値がある)”という大胆なキャッチコピーを打ち出していたんです。“これだけ払うからこそ、それ以上の履き心地を提供します”——そんな自信と誇りが感じられるメッセージでした。
[ニューバランス]自体は1906年にアメリカ・ボストンでアーチサポートインソールのメーカーとしてスタート。“履く人に最適なバランスを”という考えのもと、長年ランニングシューズを中心に技術を磨いてきたブランドです。その集大成が、この“M1300”だったわけです。
Made in USAが支えるクラフト精神

“M1300”は、いまも「Made in USA」ラインを代表するモデル。ボストン郊外のスコーヘーガン工場で、熟練した職人たちが手作業で組み立てています。
ピッグスキンスエードとメッシュの上品な組み合わせに、ENCAPミッドソールの安定感。走るための機能を持ちながら、街でも自然に馴染む。“履き心地の良さ”をここまで真剣に追求したスニーカーって、やっぱりすごいと思います。
別の広告でもこう語られていました。
“There’s a good reason why the New Balance 1300 costs more than any running shoe you’ve probably ever owned. It costs more because it offers more.”
(1300が高いのには理由がある。より多くを提供するからだ。)
価格ではなく「価値」で勝負するという、New Balanceの姿勢と自信が伝わるコピーですよね。
5年ごとに甦る、“儀式”のような復刻

“M1300”の面白いところは、5年ごとに復刻されるところ。1985年の初代モデルを皮切りに、1990年、1995年、2000年……と、ちょうど5年の周期でアップデートされたモデルがリリースされています。
そのたびに素材や技術が少しずつ進化していくのですが、基本的なデザインや履き心地の哲学は変わらない。まるで、[ニューバランス]が自分たちの原点を確かめる“儀式”のようなんですよね。
そしてもう一つ、見逃せないのが日本製の“M1300JPJ”です。これは完全ハンドメイドで作られる特別なモデルです。
限られた職人さんが、一足ずつ丁寧に仕立てていて、スエードの質感、ステッチの細かさ、履いたときの柔らかさ、どれをとっても、手仕事ならではの温かみを感じます。アメリカのクラフト哲学を受け継ぎつつ、日本の技術と感性で再構築された “M1300”の到達点”ともいえる一足です。
1985年から続く“本物”の精神

1985年に生まれた”M1300”は、時代を超えて“本物”を象徴する一足です。人の手で丁寧につくられたものが、40年経っても色あせないということを、改めて感じさせてくれます。高級スニーカーのパイオニアでありながら、いま履いても新鮮。スエードの質感やボリュームのバランス、どれをとっても完成されていると感心します。
時代が変わっても変わらない価値がある——。
そんな“M1300”のようなアイテムに出会うと、やっぱり“モノの力”ってすごいなと思います。