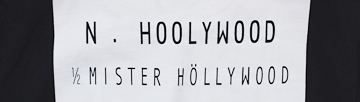No.32 「あの人に聞く 1985年」編集者 青木正一さんの場合(後編)
BACK TO 1985|
イマに続く1985年の40のコト。
RAGTAGが創業した1985年に創刊したストリートスナップ雑誌『STREET』。当時世界でも類を見なかったスナップ誌を発行したのが編集者でフォトグラファーの青木正一さんです。前編では青木さんの『STREET』発行の経緯についてお聞きしましたが、後編では東京・原宿ファッションを世界に発信したスナップ誌『FRUiTS』、『TUNE』、そして現在の活動について。
interview & text : 武井幸久(HIGHVISION)
photo : TAWARA(magNese)
Profile
青木正一
編集者、フォトグラファー
1985年にストリートスナップ雑誌の『STREET』を創刊。1996年に東京・原宿ファッションをテーマにした『FRUiTS』を創刊し、2004年にはメンズ版の『TUNE』を創刊する。日本だけでなく世界のファッションにも大きな影響力を与えたストリートファッションスナップの先駆者であり、雑誌の発行を休止している現在も、ストリートファッションをテーマに活動中。
STREET Magazine https://www.instagram.com/streetmag/
FRUiTS magazine https://www.instagram.com/fruitsmag/
- street-eo
- https://www.street-eo.com
index
突然原宿に現れた、『FRUiTS』ファッション

リアルなファッションスナップをテーマとするメディアの元祖とも言える『STREET』は、主にパリやロンドンを中心にした世界のファッションスタイルを切り取っていましたが、その後青木さんは、1996年に東京、特に原宿をテーマにしたスナップ誌『FRUiTS』を発行します。
「90年代になると『STREET』でも東京を特集した号を出したりするようになってはいたのですが、自分の中ではまだ単独の雑誌にすることは出来ないなと感じていました。ずっと原宿に事務所を構えていたものの、原宿のファッションに興味がなかったんですよ。当時はまだDCブームで[コム デ ギャルソン]、[ヨウジヤマモト]のベクトルが強くて、僕の中では『誰を撮ってもカッコいいけど、同じじゃん』と。ただ、『STREET』を始めて10年くらい経った頃に、突然現れたんですよ」

青木さんが「突然現れた」と表現するのは、まさに青木さんの次なる雑誌『FRUiTS』の世界観を持った、個性的なファッションの若い世代の男女たち。
「誰かが仕掛けたわけでもないし、何か特定のブランドが流行っているわけでもない。そういう中で原宿の子たちがそういう格好をしているのに気がついて。それは誰の目にも明らかだったと思うんですけど、時々外国人観光客が面白がって撮っていたくらいで、誰もフィーチャーしていなかったんです。『これは日本のファッション革命になるのかな』と気づいて、記録しなきゃいけないと思い始めたんです。でも、街に出れば誰でも分かることなので、毎号出しても売れるのかな?と思いましたけど、記録して残すという “使命感” のような気持ちでやることにしたんです」
青木さんのアンテナに引っかかった原宿の若い世代のファッションスナップは、青木さんの当初の想定を超えて大ヒット。一時期は10万部という部数を叩き出す雑誌として、ファッション雑誌市場に新たな潮流を生み出します。

「彼ら彼女らも、最初こそ[ミルク]とか[ミルクボーイ]、[ヴィヴィアンウエストウッド]とか、ブランド志向はありました。あとは『STREET』の功績もあるかもしれないけど、ロンドンのストリートファッションの影響もあったと思います。それからもう一つには、髪の毛が緑とかピンクに染められるようになったタイミングもあると思うんです。実はそこの影響も大きかった。当時は美容師さんが影響力を持っていた時期で、美容師さんは修行などでみんなロンドンに行くじゃないですか。彼らはストリートのこともよく知っていたし、髪の毛を染めるテクニックも知っていたんです」

青木さんは東京での撮影の際に声をかけるようになりましたが、あくまでも興味があったのは、その人のファッション。しかし、実際に話をしてみると、本人たちがかなり考えてそのコーディネートに取り組んでいることに気づいたそうです。
「その人の着こなし、アウトプットを見れば、誰かの真似をしているのも分かっちゃうし、やりたいことも能力も全部分かります。“こなし方” というのは分析できない不思議な部分なんですけど、本人たちはちゃんと分かってやっているんですよね。『なんでそれにしたの?』って聞くと、明確に答えるんで。努力もしているし、レベルが深いんですよ」
青木さんから見た裏原宿ファッション

90年代から2000年代前半の原宿といえば、「裏原宿」ファッションが花開いた時期でもあります。そうした中で、青木さんは“裏原”をどう見ていたのでしょうか。
「その存在はずっと知っていました。『青木さん、これからはエイプ([ア ベイシング エイプ])ですよ』とか言われるようになって、『ノーウェア』のお店とかにも行ってみたんですけど、恐る恐る店に入ったらTシャツが一枚かかっているだけみたいな(笑)。そしてある時期から『FRUiTS』で[ヴィヴィアン]や[クリストファーネメス]を着て出ていたような男の子たちが、一瞬で全員“裏原”になったんです」
青木さんが『FRUiTS』でピックアップしたような原宿ファッションが盛り上がりを見せる一方、同時多発的に生まれた裏原ファッション。この時期の原宿がいかに活気に溢れていたかを物語りますが、青木さんとしては裏原ファッションとは少し距離を置いて見ていたそうです。
「“裏原” は、どこのブランドで、どことコラボして、限定で、並ばないと買えないとか、二次流通でも値段が上がるとか、ファッションにそういう “ゲーム” 性を加えたんじゃないかと思います。それはビジュアルのファッションではなく、“情報” なんですよね。でも、一番オシャレな子たちからそういうファッションに変わって行ったんで、そこの訴求も上手かったんだと思います。世界でもそれをやった最初の人たちだと思うし、その凄さも分かります。今になってハイブランドの人たちが裏原ファッションに注目しているのはそういう背景もあるのでしょう。ただ、当時特に男の子はそういう感じに変わって行ったんで、『FRUiTS』には馴染まなくなって、だんだん『FRUiTS』は女の子の雑誌になって行くんです。創刊号は男女半々くらいだったんですけどね」
また青木さんは、アート的な視点でも裏原ファッションを鋭く分析します。
「当時の『FRUiTS』は視覚のファッションだったんですけど、裏原ファッションというのはそうじゃないんですね。思想的なルーツは藤原ヒロシさんだと思うのですが、それはマルセル・デュシャンが『網膜的(ビジュアル的)なアートはダサい』と言い出して、ああいうこと(EX : 既製品の便器を美術展に出品。『泉』など)をやり始めた感じに近いと思うんです。聞いてみないと分からないけど、意識してやられたんじゃないかなと思うんですよね」
10年周期で現れる、新しい潮流

雑誌『FRUiTS』で日本のファッションの中に新しい “トライブ” を築いた青木さんは、2004年に新たな雑誌『TUNE』を世に送り出します。『TUNE』は主に男性ファッションにフィーチャーし、その時期に生まれたメンズファッションの新たな潮流を捉えました。
「僕の雑誌は10年ごとに出る傾向にあるんですが、『TUNE』も『FRUiTS』をやって10年くらいの時期です。それって “裏原ファッションの支配が10年続いた”、ということだと考えているのですが、また男性の中にも網膜的、ビジュアル的ファッションが急に生まれたんです。おそらく『カンナビス』というお店やスタッフの存在が大きいのですが、急に『もう5年も10年もこういう格好をしてますよ』というような、“こなし” に優れた子たちが現れた。僕からすると数年試行錯誤して辿り着くようなファッションなので、今でも謎だし驚きなんですけど、また『FRUiTS』とは違うニュアンスなんで、別の雑誌にしようということで『TUNE』が始まりました」

1985年に『STREET』、1996年に『FRUiTS』、2004年に『TUNE』と、ライフテーマである “ストリートファッション” と “メディア” を具現化してきた青木さんですが、2015年に『TUNE』を、そして2016年に『FRUiTS』を休刊にしています。
「『FRUiTS』は撮るべき人がいなくなっちゃったというのが大きいですね。ファストファッションブームで原宿ファッションが全然面白くなくなっちゃったんです。『TUNE』の方は単純に雑誌が売れなくなったというのが大きいと思います。ちゃんと書店取次の販売ルートだったので、なかなかすぐに止めることが出来ずにズルズルやっていたんですけど、ビジネス的にももう少し早くやめるべきだったと思います。ただ、自分の中では “ストリートファッション” というテーマがあるので、やめるのは苦渋の決断ではありました。デジタルによって、雑誌メディア自体ダメになるとは想像していなかったですよね」
世界を見回しても、原宿にはまだまだ可能性がある

近年改めて世界的にも評価が高まっている、『STREET』、『FRUiTS』、『TUNE』の3誌や青木さんの功績。アーカイブ集などの発行も視野に入れて活動をしながら、青木さんは現在でもライフテーマである “ストリートファッション” と “メディア” について、追い続けています。
「『STREET』はやろうと思えば出来るんですけど、ファッションウィークの外の “狂騒” みたいなのに飽きちゃっているというか、見てて嫌になっているかもしれないですね。今はストリートスタイルフォトグラファーの人が100人くらいいるんですよ。モデルやタレントの人も撮られる気満々で出てきますし、数十人が取り囲んで『もう一回歩き直して!』みたいな中に僕が入って撮るのもなあって。当時は僕ひとりだったので、寂しい思いはしていたんですけど(笑)。ただ、『FRUiTS』に関しては、少し可能性を感じています」
青木さんが感じる“可能性”とは、どこから生まれてくるものなのでしょうか?
「最近ソウルや上海、ニューヨークに行ったりしているんですけど、ファッション的には原宿 “だけ” が面白いと思います。こんな変な街はないですよ(笑)。海外の都市でもファッションウィークにはものすごくオシャレな子たちはいますが、普通の人はほとんどオシャレをしていない。でも原宿だけは “普通の人” がオシャレをしているんですよね。もちろんレベルの差はありますけど、ほとんどの人からはちゃんとオシャレで表現しようという “メッセージ” が伝わってくるんです。その汲み取り方は考えないといけないけど、そろそろなんとかしなきゃなとは思っています」
現在に至るまで原宿に事務所を構え、今も原宿界隈を見続けている青木さんは、ファッションの発信地であるこの街に対してもひとつのリクエストがあるそうです。
「昔の原宿は、座っていたり、佇んでいる子がいっぱいいたんです。そういう子たちを撮るのが好きだったのですが、そういう場所がどんどん “無くされてしまった” 気がします。以前明治神宮前の交差点にあった『Gap』とか、今考えるとすごいじゃないですか。普通だったら『お店に入る人の邪魔になるから座らないでください』と言うようなところだったのに、何も言われなかった。またああいう場所があるといいなと思って、色んな人に言っているんですけどね」
現在青木さんは、これまでの雑誌のデジタルアーカイブなどを進める一方、原宿の事務所を改装し、ポップアップやギャラリーとしての活用を模索中。また、原宿の街で開催するファッションイベントなども構想しているそうです。40年にも渡り、独特の立ち位置でストリートファッションを発信し続ける青木さんから生み出されるカルチャーの歴史は、この先もまだまだ続きそうです。